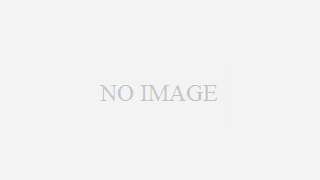 家電
家電 HUAWEI WATCH GT 5 PRO 46MMの評判は?14日バッテリー・通話対応・高級感の魅力とは
「スマートウォッチは便利だけど、見た目がどうしても安っぽい…」そんな風に感じていた方に朗報です。HUAWEI WATCH GT 5 PRO 46MMは、高級感のあるデザインと本格的な機能性を兼ね備えた、今注目のスマートウォッチです。最大14...
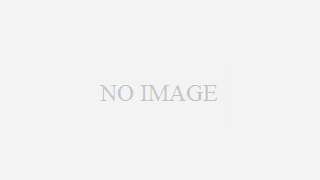 家電
家電  サービス
サービス  楽天
楽天 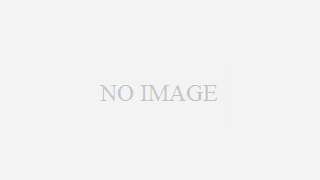 未分類
未分類  家電
家電